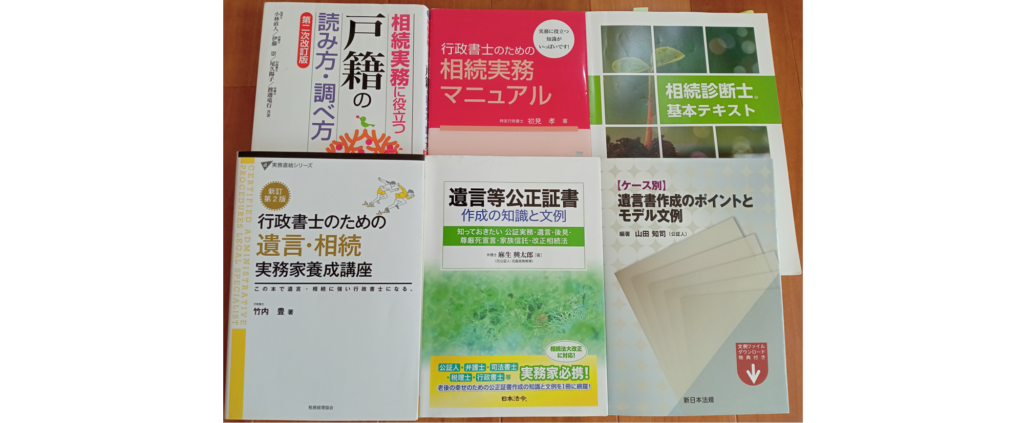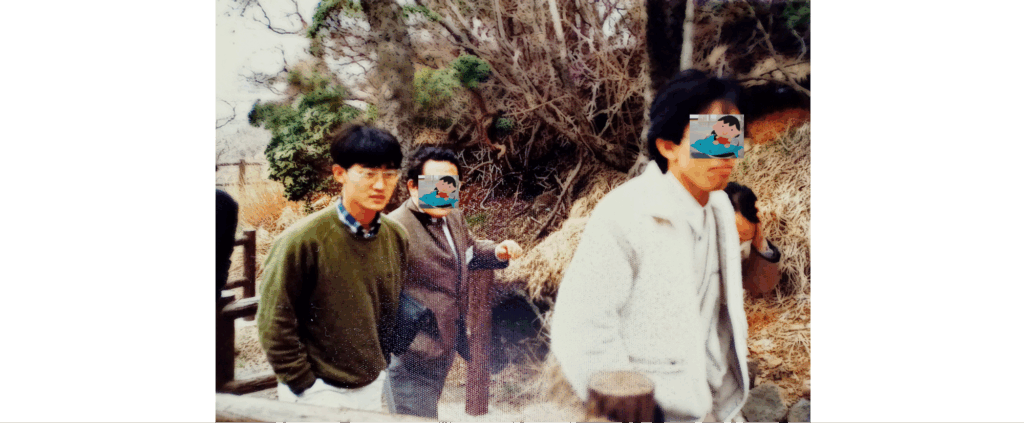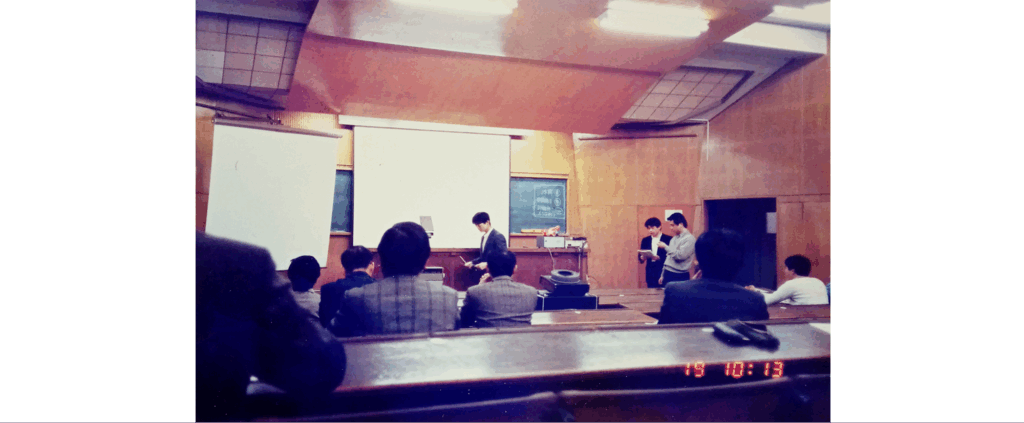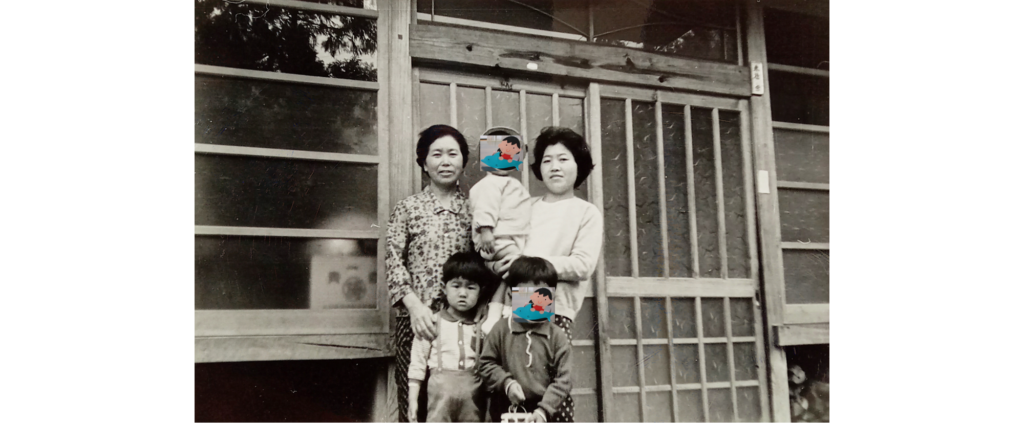
【遺言:遺産分割方法の指定について】
遺言で相続人に指定した相続分の割合で遺産を相続させることができます。
預貯金の場合、各相続分で割ることができます。
しかし、建物、自動車などは物理的に割ることができません。
そこで遺産をどう分けるか遺言で決めることを遺産分割方法の指定といいます。
たとえば、相続人が配偶者と子二人の場合、「配偶者に不動産を相続させて、子2人に預貯金を2分の1ずつ相続させる」と遺言書で決めることができます。
遺産分割には、次の通りの分け方があります。
①現物分割
②代償分割
③換価分割
①現物分割
現物分割とは、各財産をそのまま各相続人に相続させる分割方法です。
たとえば、不動産を長男に相続させて預貯金を次男に相続させる、土地を分筆して各相続人に相続させる場合などです。
②代償分割
代償分割とは、特定の相続人に不動産・動産を相続させる代わりに、その特定の相続人がほかの相続人に対して金銭などを支払う分割方法です。
たとえば、長男に不動産を相続させる代わりに、長男が次男に代償金を支払うようなケースです。
相続財産が建物など、物理的に分割しにくいものが多く、現預金など分割しやすいものがあまりないような場合に使われます。
③換価分割
換価分割とは、相続財産を売却して、売却代金を分割する方法です。
たとえば、相続財産である不動産を売却して、売買代金を各相続人が分割する方法です。
相続財産に自宅不動産があるけども、相続人が誰も住む予定がない場合に使われます。
もし遺言で遺産分割方法を指定しなかったら被相続人が亡くなった後に相続人同士で遺産分割の方法を話し合うことになります。
【遺言:遺産分割方法の指定の委託について】
遺言を書く時点では遺言者の方が家族に財産の全て、或いは、一部をどのように分割させて相続させた方が良いか悩まれているかもしれません。
そのような場合などに遺言で相続財産の分割を第三者に委託することができます。
例えば、ある特定の遺産を長男に「相続させる」趣旨の遺言をしたうえで、残りの遺産を他の相続人らに分割するにつき、遺産分割の方法をこの長男に委託することができます。
ただし、残りの遺産に関する遺産分割の方法に限られます。長男に全ての遺産の分割の方法を委託すると自分に都合の良い形で分割の方法を決めることができてしまうためです。そのため第三者は、信義則上相続に関係しない者である必要があります。
第三者として指名された方は相続分の分割方法の指定を拒否することが可能です。
第三者が遺産の分割方法のを定せずに放置している場合、相続人は第三者に遺産の分割方法の指定の諾否又は催告をできます。この催告をしたにもかかわらず、相当の期間のうちに第三者が遺産の分割方法の指定をしない場合は、遺言による指定の委託は効力を失い、法定相続分に従った相続になります。
遺言書において遺産の分割方法の指定を委託する場合、第三者の方が委託を受け入れてくれるかどうか確認されることをお薦めします。
第三者へ遺産の分割方法の指定を委託する際に「相続人らの職業、年齢、経済状態等の一切の事情を考慮し、公平に遺産の分割方法の指定がなされることを希望する」などと遺言書に記載することが可能です。