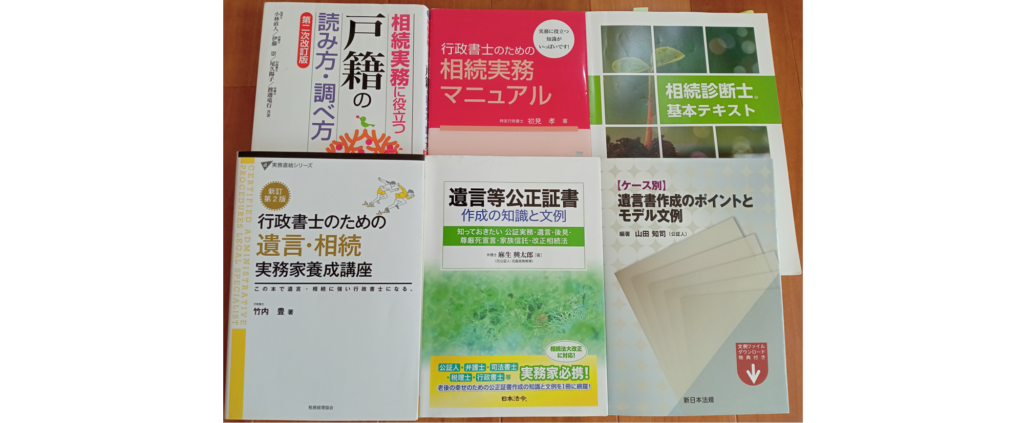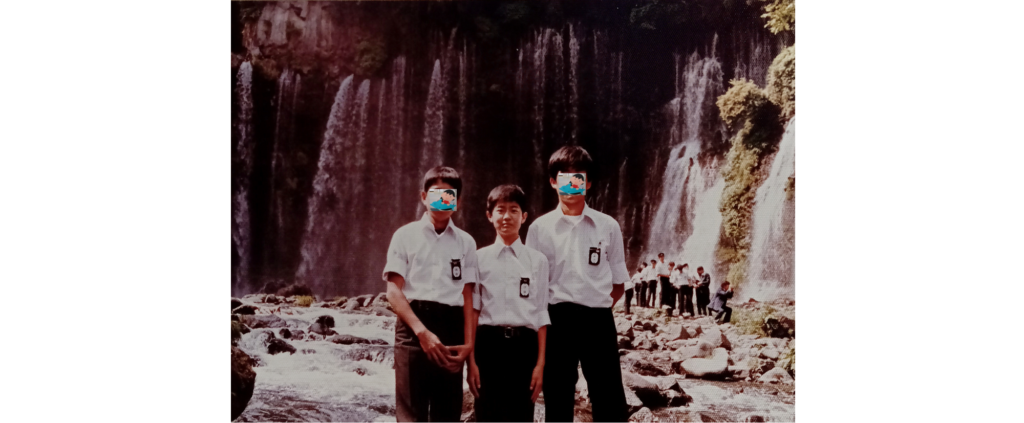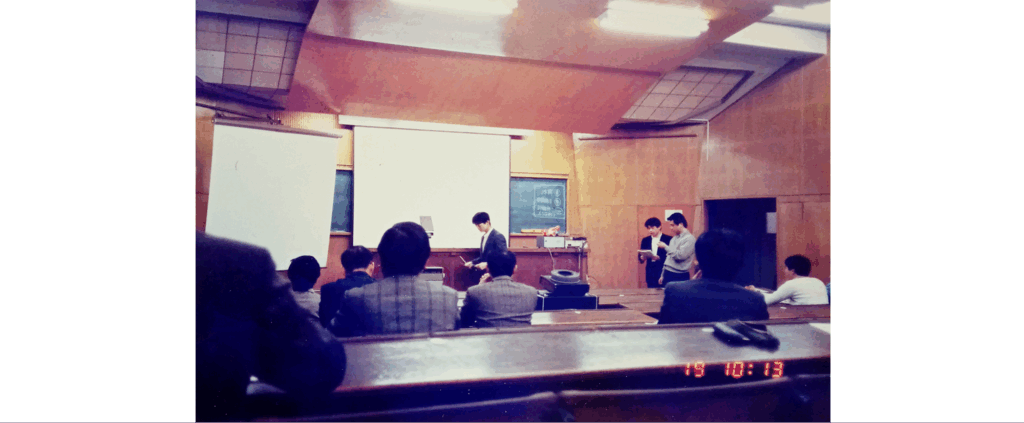妻の生活費の負担付遺贈の自筆証書遺言書の書き方
遺言書
遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。
1 私は、その有する現金及び預貯金、株式等一切の金融資産を、日永愛子(生年月日、住所)に遺贈する。
2 受遺者日永愛子は、1記載の財産の遺贈を受ける負担として、私の妻伊藤花子(生年月日)に対し、同人が生存中その生活費として月額10万円ずつを毎月末日限り同人の住所に持参又は送金して支払うこと。
ペットの世話の負担付遺贈の自筆証書遺言書の書き方
遺言書
遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。
1 私は、その有する金600万円を日永愛子(生年月日、住所)に遺贈する。ただし、日永愛子は、前記財産の遺贈を受ける負担として、私の愛犬コロを生涯にわたり、介護扶養し、死亡の場合は、相当な方法で埋葬、供養しなければならない。
ペットには権利能力はありませんので、「私は、その有する金600万円を愛犬コロ(生年月日、住所)に遺贈する。」という遺言をしても無効となります。
負担付遺贈とは
負担付き遺贈とは、受遺者(上記例の日永愛子)に一定の法律上の義務を負担させる遺贈のことです。受遺者(日永愛子)は、遺贈の目的の価額(上記例のその有する現金及び預貯金、株式等一切の金融資産)を越えない限度において負担した義務を負います(民法1002条1項)。遺言者は受遺者(日永愛子)の負担が過重にならないように遺贈の目的の価額と負担の内容について受遺者(日永愛子)と予め相談してから負担付遺贈の遺言をされた方が良いです。
尚、不動産の遺贈を受けた場合はその所有権移転登記をしないと第三者に対抗できません。
受遺者が負担を履行しない場合
受遺者(日永愛子)が負担を履行しない場合、相続人及び遺言執行者は、相当の期間を定めてその履行の催促をすることができ、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます(民法1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)、1012条(遺言執行者の権利義務)、1015条(遺言執行者の行為の効果))。
負担付遺贈が取り消された場合は、負担付遺贈はなかったことになります。そして、その対象財産は、相続人に帰属します(民法995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属))。
負担付受遺者の遺贈の放棄
受遺者(日永愛子)は、遺贈を受託する義務はなく、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができます(民法986条1項(遺贈の放棄))。遺贈の放棄は特定遺贈に限られます。包括遺贈を放棄する場合は、相続の放棄に関する規定(民法938条(相続の放棄の方式)から940条(相続の放棄をした者による管理))が適用されます。受遺者(日永愛子)が遺贈を放棄したときは、負担の利益を受けるべき人(受益者、伊藤花子)が、自ら受遺者となることができます。ただし、遺言者が遺言で別段の定めをしておけば、それに従うことになります。(民法1002条2項(負担付遺贈))
妻と同居、扶養の負担付相続の自筆証書遺言書の書き方
遺言書
遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。
1 私は、その有する不動産、現金、預貯金、株式等一切の財産を、私の長男伊藤一郎(生年月日)に相続させる。ただし、長男伊藤一郎は、私の一切の財産を相続することの負担として、私の妻伊藤花子(生年月日)が死亡するまで同人と同居し、同人を扶養しなければならない。
ペットの世話の負担付相続の自筆証書遺言書の書き方
遺言書
遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。
1 私は、その有する不動産、現金、預貯金等一切の財産を、私の長男伊藤一郎(生年月日)に、相続させる。ただし、伊藤一郎は、前記財産の相続を受ける負担として、私の愛犬コロを生涯にわたり、介護扶養し、死亡の場合は、相当な方法で埋葬、供養しなければならない。
遺言書を作成しても、ご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です
遺言書を作成すると、その遺言と矛盾する財産処分はできなくなると思い込んでいる方もいらっしゃいますが、遺言者の方がご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です。遺言書の内容に縛られることはありません。例えば、「長男に土地・建物を相続させる」と遺言書に記載しても、土地・建物を売却することは可能です。この場合、「長男に土地・建物を相続させる」という遺言が撤回されて、遺言執行ができなくなるだけです。遺言書を作成されることのデメリットは一切ありませんので、ご安心願います。
遺言に関するご相談はひなが行政書士事務所まで
四日市市、鈴鹿市の皆さま 公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の作成支援、公証役場での遺言の証人、遺言執行者の就任、遺言の無料出張講座をいつでも承ります。ひなが行政書士事務所までお気軽にご相談下さい。
遺言書の専門知識チェッククイズ
**【問題】** あなたは遺言書を作成しようとしています。この記事の解説に基づき、次の遺言文のうち、**民法上、遺言として成立しないため無効となるものはどれですか?**
自筆証書遺言の関連記事
・自筆証書遺言の長所、短所、法的要件は別記事「自筆証書遺言について」を参照願います。
・自筆証書遺言の保管申請制度の利用をお考えの方は、別記事「自筆証書遺言の保管申請制度の利用方法について説明します!」を参照願います。
1 自筆証書遺言書の書き方(基本型、遺産の全部を相続させる、遺産の全部を包括して遺贈する遺言)
4 一筆の土地を具体的に分割して相続させる自筆証書遺言書の書き方
6 増築部分が未登記の建物を相続させる自筆証書遺言書の書き方
9 将来相続によって取得する財産を遺言で相続させる場合の自筆証書遺言書の書き方
参考資料
・自筆証書遺言書保管制度のご案内(法務省民事局、令和5年1月作成)
・遺言等公正証書 作成の知識と文例(麻生興太郎著、日本法令、令和5年5月10日)
・改定増補版 行政書士のための相続実務マニュアル(初見 孝著、三省堂書店/創英社、令和7年4月12日)
・【ケース別】遺言書作成のポイントとモデル文例(山田知司編著、新日本法規、令和4年12月9日)