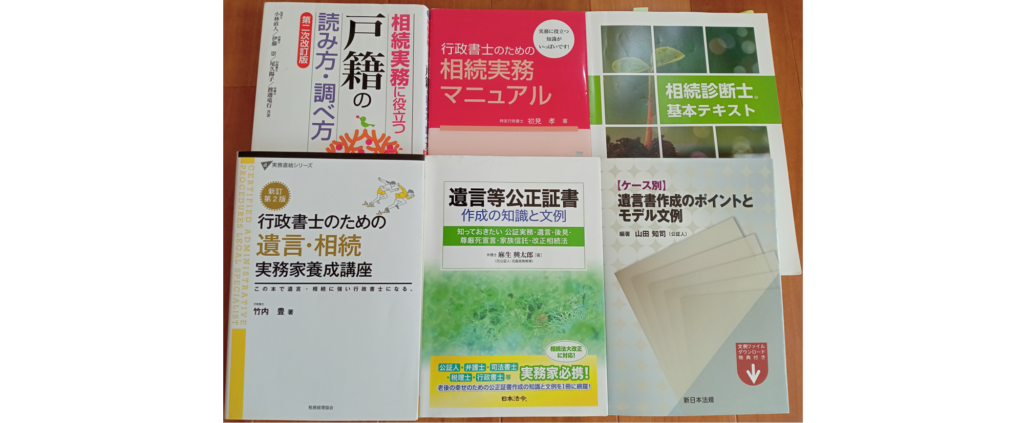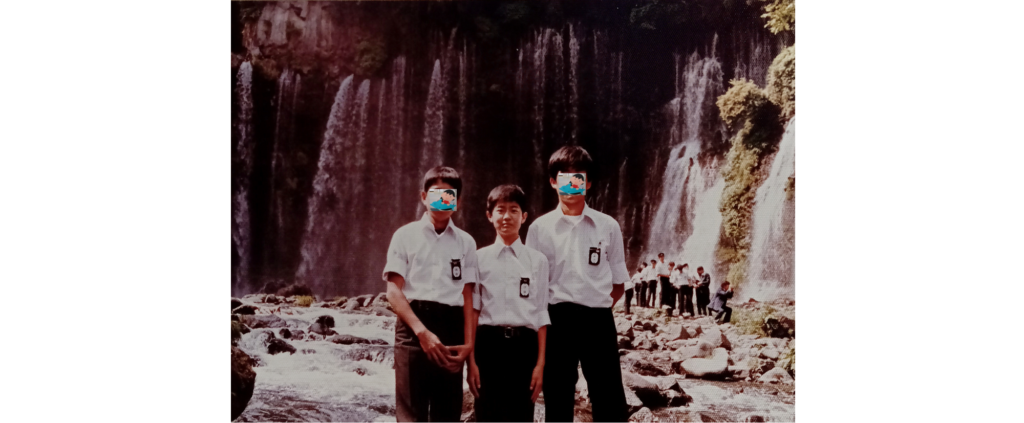将来相続によって取得する財産を遺言で相続させる場合の自筆証書遺言書の書き方
CASE1
遺言書
遺言者 伊藤花子は次のとおり遺言する。
1 私は、夫伊藤太郎(生年月日)が死亡した場合に同人から相続すべき別紙1の不動産を、私の長女伊藤一子(生年月日)に相続させる。
別紙1の不動産:所在、地番、家屋番号等により不動産を特定できれば、登記事項証明書(登記簿謄本)の一部分や縮小したコピー、登記情報提供サービスを利用した印刷物を財産目録として添付することができます。不動産が未登記でも固定資産課税評価証明書、名寄帳のコピーを添付することができます。自書によらない財産目録を添付する場合は、そのページごとに署名し、押印する必要があります。署名は自書する必要があります。左上に「別紙1」と記載します。
※遺言者が死亡するまでに相続で取得する可能性のある財産について、遺言に記載することができます。
CASE2
遺言書
遺言者 伊藤花子は次のとおり遺言する。
1 私は、夫伊藤太郎(生年月日)が死亡して同人から相続を受けた場合は、その相続を受けた財産のうち、不動産の一切は私の長男伊藤一郎(生年月日)に相続させ、金融資産の一切は私の長女伊藤一子(生年月日)に相続させる。
2 私は、私が固有に有する金融資産の一切は私の二女伊藤二子に相続させる。
夫が妻に遺言で相続させる不動産を、妻の死亡後は、長女に相続させたい場合の自筆証書遺言の書き方
夫の遺言書の書き方
遺言書
遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。
1 私は、その有する別紙1の不動産を、私の妻伊藤花子(生年月日)に相続させる。
(付言) 妻伊藤花子は、1記載の不動産を相続したときは、その不動産は、長女伊藤一子に相続させてください。
別紙1の不動産(上述)
妻の遺言書の書き方
遺言書
遺言者 伊藤花子は次のとおり遺言する。
1 私は、私の夫伊藤太郎(生年月日)が死亡した場合に同人から相続すべき別紙1の不動産を、私の長女伊藤一子(生年月日)に相続させる。
別紙1の不動産(上述)
以上のように、夫婦の二人が同時に遺言書を作成すれば、夫の希望は実現できます。ただし、一旦妻に相続させて妻に帰属した不動産を、妻がどのように処分しようと自由ですので、長女への相続を確実にするために跡継ぎ遺贈型受益者連続信託を活用する方法もあります。
跡継ぎ遺贈型受益者連続信託とは
受益者【夫】の死亡により当該受益者【夫】の有する受益権【自宅の土地・建物に無償で居住できる】が消滅し、他の者【妻】が新たな受益権【自宅の土地・建物に無償で居住できる】を取得する旨の定め(受益者【妻】の死亡により順次他の者【長女】が受益権【自宅の土地・建物に無償で居住できる】を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者【長女】が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者【長女】が死亡するまで又は当該受益権【自宅の土地・建物に無償で居住できる】が消滅するまでの間、その効力を有する。(信託法91条)
遺言書を作成しても、ご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です
遺言書を作成すると、その遺言と矛盾する財産処分はできなくなると思い込んでいる方もいらっしゃいますが、遺言者の方がご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です。遺言書の内容に縛られることはありません。例えば、「長男に土地・建物を相続させる」と遺言書に記載しても、土地・建物を売却することは可能です。この場合、「長男に土地・建物を相続させる」という遺言が撤回されて、遺言執行ができなくなるだけです。遺言書を作成されることのデメリットは一切ありませんので、ご安心願います。
自筆証書遺言の関連記事
・自筆証書遺言の長所、短所、法的要件は別記事「自筆証書遺言について」を参照願います。
・自筆証書遺言の保管申請制度の利用をお考えの方は、別記事「自筆証書遺言の保管申請制度の利用方法について説明します!」を参照願います。
1 自筆証書遺言書の書き方(基本型、遺産の全部を相続させる、遺産の全部を包括して遺贈する遺言)
4 一筆の土地を具体的に分割して相続させる自筆証書遺言書の書き方
6 増築部分が未登記の建物を相続させる自筆証書遺言書の書き方
参考文献
・自筆証書遺言書保管制度のご案内(法務省民事局、令和5年1月作成)
・遺言等公正証書 作成の知識と文例(麻生興太郎著、日本法令、令和5年5月10日)
・行政書士のための相続実務マニュアル(初見 孝著、三省堂書店/創英社、令和4年9月30日)