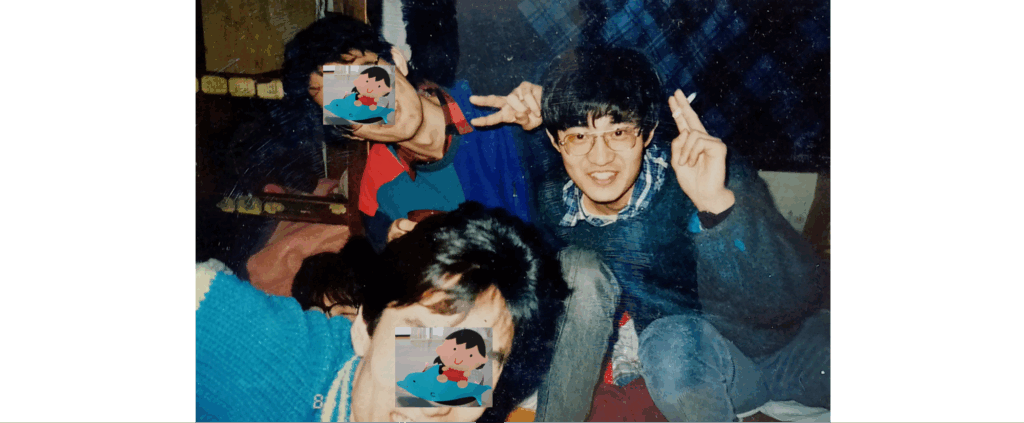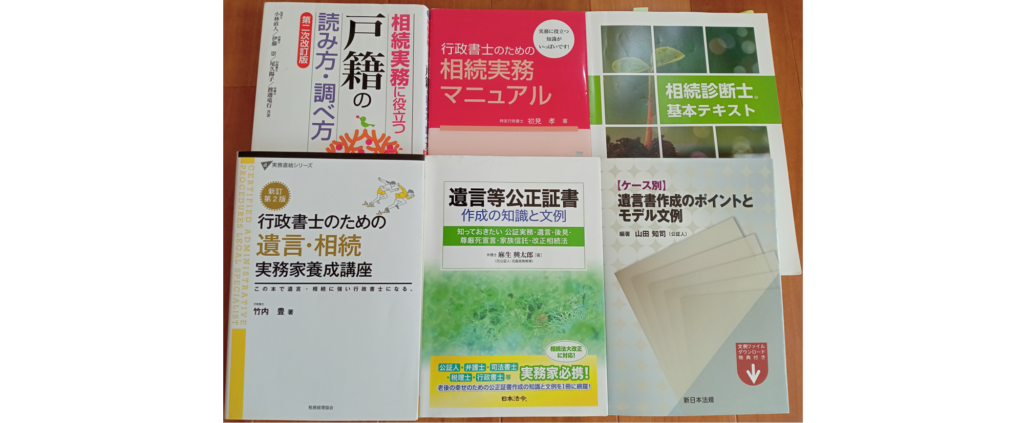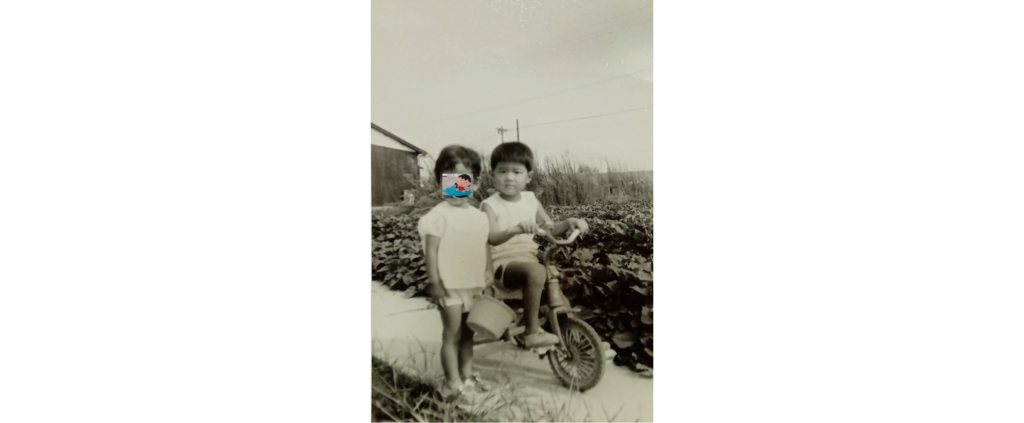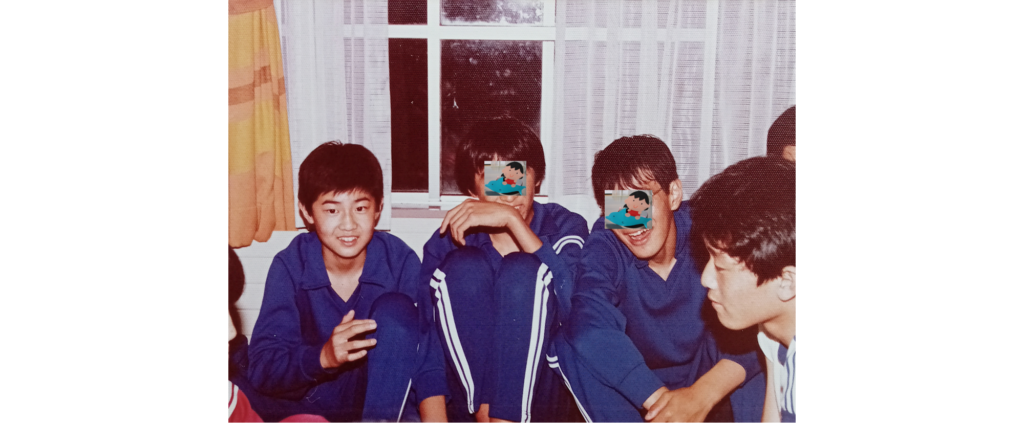清算型自筆証書遺言の書き方
遺言書
遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。
1 私は、その有する不動産の一切を換価し、その換価金から不動産を処分する費用(建物解体、不動産登記等)を控除した金額と、その有する預貯金等金融資産の一切を換金した金額の合計金額から、その一切の債務を弁済し、私の葬儀・埋葬費用を控除した残金を、下記のとおり配分する。
妻 伊藤花子(生年月日)に6分の4
長男 伊藤一郎(生年月日)に6分の1
二男 伊藤二郎(生年月日)に6分の1
2 私は、本遺言の遺言執行者として、私の長男伊藤一郎(生年月日)と下記の者を指定する。
住所 三重県四日市市日永〇〇〇〇番地〇〇〇
職業 行政書士
氏名 伊藤〇〇
生年月日 昭和〇年〇月〇日
3 遺言執行者は、単独で、本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
(1)不動産の一切の名義変更及び不動産の売却に関する一切の行為(建物解体、不動産登記等)
(2)預貯金等金融資産の一切の名義変更、払戻、解約
(3)貸金庫の開扉、解約、内容物の受領・管理
(4)その他遺言執行のために必要な一切の権限
3 遺言執行者は、本遺言の執行に関し第三者にその任務の全部又は一部を行わせることができる。
清算型遺言について
・遺言者の有する不動産の売却や預貯金の払い戻し等、全財産を換価して、その換価金を相続人に相続させるのが換価分割です。
・相続財産に関する費用(民法885条)と遺言の執行に関する費用(民法1021条)は、遺言に記載しなくても相続財産の負担になります。
・遺言者の葬儀・埋葬費用は遺言者の債務ではありませんが、上記文例のように遺言により相続財産から支払うと定めることもできます。
・清算型遺言は相続人以外の方に配分して遺贈することもできます。
・特定の財産を特定の相続人に相続させ又は特定の者に遺贈して、残りの財産を換価して配分することもできます。
民法885条(相続財産に関する費用)
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
民法1021条(遺言の執行に関する費用の負担)
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
清算型遺言では遺言執行者を指定しましょう
清算型の換価分割の遺言において、遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は、不動産を相続人の名義で売却し、相続人全員の相続登記をした上、遺言執行者と買受人との共同申請で買受人への所有権移転登記を行うことができます。遺産の換価、清算、配分を相続人に共同でさせるのは妥当ではないことが多く、遺言を実行するには専門的な知識や経験が必要ですので、清算型遺言の遺言執行者は、行政書士等の専門家を指定されるとよいです。遺言執行者が指定されると、遺産は全て遺言執行者の管理下に置かれ(民法1012条)、相続人には遺産の管理処分権はありません(民法1013条)
民法1012条(遺言執行者の権利義務)
① 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
② 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
③ 第644条(受任者の注意義務)、第645条から第647条(受任者による報告、受任者による受取物の引渡し等、受任者の金銭の消費についての責任)まで及び第650条(受任者による費用等の償還請求等)の規定は、遺言執行者について準用する。
民法1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
① 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
② 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
③ 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
遺言書を作成しても、ご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です
遺言書を作成すると、その遺言と矛盾する財産処分はできなくなると思い込んでいる方もいらっしゃいますが、遺言者の方がご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です。遺言書の内容に縛られることはありません。例えば、「長男に土地・建物を相続させる」と遺言書に記載しても、土地・建物を売却することは可能です。この場合、「長男に土地・建物を相続させる」という遺言が撤回されて、遺言執行ができなくなるだけです。遺言書を作成されることのデメリットは一切ありませんので、ご安心願います。
自筆証書遺言の関連記事
・自筆証書遺言の長所、短所、法的要件は別記事「自筆証書遺言について」を参照願います。
・自筆証書遺言の保管申請制度の利用をお考えの方は、別記事「自筆証書遺言の保管申請制度の利用方法について説明します!」を参照願います。
1 自筆証書遺言書の書き方(基本型、遺産の全部を相続させる、遺産の全部を包括して遺贈する遺言)
4 一筆の土地を具体的に分割して相続させる自筆証書遺言書の書き方
6 増築部分が未登記の建物を相続させる自筆証書遺言書の書き方
9 将来相続によって取得する財産を遺言で相続させる場合の自筆証書遺言書の書き方
参考文献
・自筆証書遺言書保管制度のご案内(法務省民事局、令和5年1月作成)
・遺言等公正証書 作成の知識と文例(麻生興太郎著、日本法令、令和5年5月10日)
・行政書士のための相続実務マニュアル(初見 孝著、三省堂書店/創英社、令和4年9月30日)