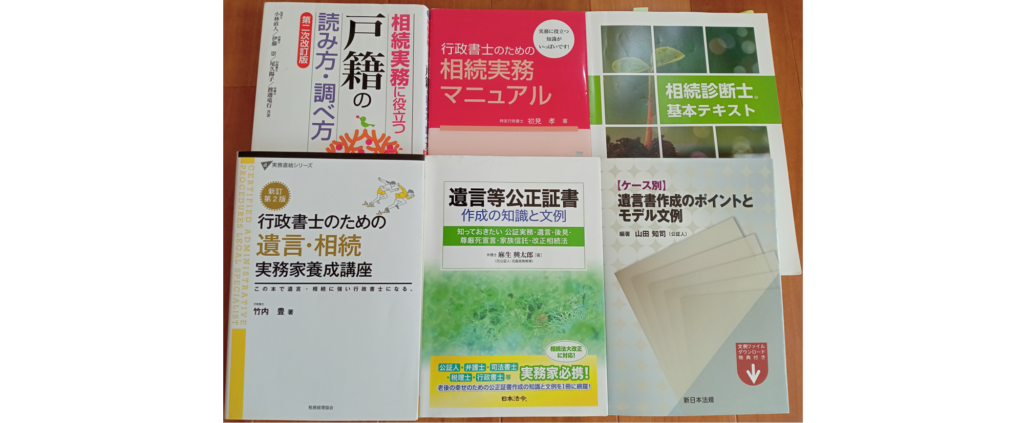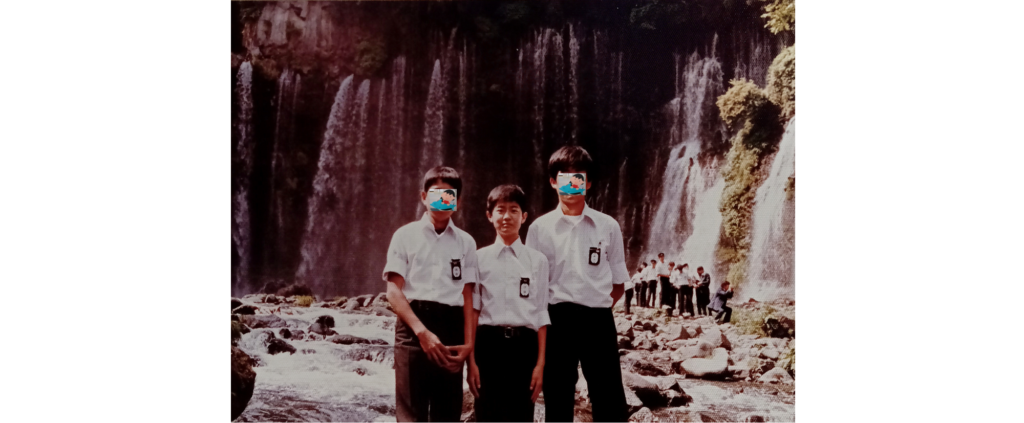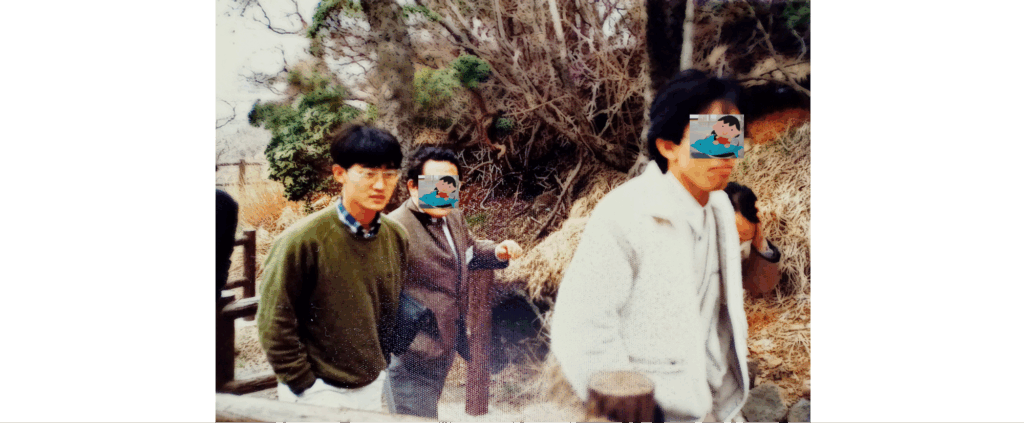相続分を指定する自筆証書遺言の書き方
遺言書
遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。
1 私は、次のとおり相続分を指定する。
妻 伊藤花子(生年月日)に6分の4
長男 伊藤一郎(生年月日)に6分の1
二男 伊藤二郎(生年月日)に6分の1
残された家族のために付言に相続分を指定された理由を書かれた方が良いです。
また、遺留分を侵害する相続分の指定がなされた場合は、遺留分侵害額請求権の行使の対象になりますので、ご注意願います(民法1046条①、1047条①)。
第1046条(遺留分侵害額の請求)
① 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)
① 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条(遺留分の帰属及びその割合)の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者(逝去時)と受贈者(逝去前)とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
相続分の指定とは
遺言者は、法定相続分の規定にかかわらず遺言で共同相続人の相続分を定めることができます(民法902条①)。
遺言によって指定相続分を定めた場合は、民法の法定相続分よりも優先します。
相続分の指定は遺言以外ではすることができません。
各相続人の置かれた状況を考えた上、遺留分を侵害しないように相続分を指定しましょう。
また、相続分を指定した場合、遺言に従って相続財産をどのように分割するか相続人の間で遺産分割協議を行わなければなりません。遺産分割協議がまとまらない可能性があることをご留意願います。
第902条(遺言による相続分の指定)
① 被相続人は、前二条(法定相続分、代襲相続人の相続分)の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
【不動産の法定相続分を超える部分については登記しなければ第三者に対抗できません】
遺言による相続分の指定であっても不動産を相続した場合、法定相続分は登記がなくても第三者に対抗できますが、法定相続分を超える部分については登記がなければ第三者に対抗できません(民法899条の2①)。従って、速やかに不動産登記を行うことをおススメします。
第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
① 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
相続債務と相続分の指定との関係
相続債務(借金など)については指定相続分の割合に従って相続します。
しかし、債権者(金融機関など)が法定相続分に応じて、各共同相続人に債務の履行(借金の返済など)を請求した場合は、各共同相続人は法定相続分に応じて債務の履行(借金の返済など)をしなければなりません。
ただし、債権者(金融機関など)が相続分の指定を認めた場合、各共同相続人は相続分の指定に応じて債務の履行(借金の返済など)をすることができます。
遺言書を作成しても、ご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です
遺言書を作成すると、その遺言と矛盾する財産処分はできなくなると思い込んでいる方もいらっしゃいますが、遺言者の方がご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です。
遺言書の内容に縛られることはありません。
例えば、「長男に土地・建物を相続させる」と遺言書に記載しても、土地・建物を売却することは可能です。
この場合、「長男に土地・建物を相続させる」という遺言が撤回されて、遺言執行ができなくなるだけです。
遺言書を作成されることのデメリットは一切ありませんので、ご安心願います。
遺言に関するご相談はひなが行政書士事務所まで
四日市市、鈴鹿市の皆さま 公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の作成支援、公証役場での遺言の証人、遺言執行者の就任、遺言の無料出張講座をいつでも承ります。ひなが行政書士事務所までお気軽にご相談下さい。
クイズ
【相続分指定クイズ】
遺言書で相続分を指定した際、亡くなった方(被相続人)の借金(相続債務)についても、指定された割合に従ってのみ債権者(銀行など)は返済を請求できるのでしょうか?
自筆証書遺言の関連記事
・自筆証書遺言の長所、短所、法的要件は別記事「自筆証書遺言について」を参照願います。
・自筆証書遺言の保管申請制度の利用をお考えの方は、別記事「自筆証書遺言の保管申請制度の利用方法について説明します!」を参照願います。
1 自筆証書遺言書の書き方(基本型、遺産の全部を相続させる、遺産の全部を包括して遺贈する遺言)
4 一筆の土地を具体的に分割して相続させる自筆証書遺言書の書き方
6 増築部分が未登記の建物を相続させる自筆証書遺言書の書き方
9 将来相続によって取得する財産を遺言で相続させる場合の自筆証書遺言書の書き方
参考文献
・自筆証書遺言書保管制度のご案内(法務省民事局、令和5年1月作成)
・遺言等公正証書 作成の知識と文例(麻生興太郎著、日本法令、令和5年5月10日)
・行政書士のための相続実務マニュアル(初見 孝著、三省堂書店/創英社、令和4年9月30日)