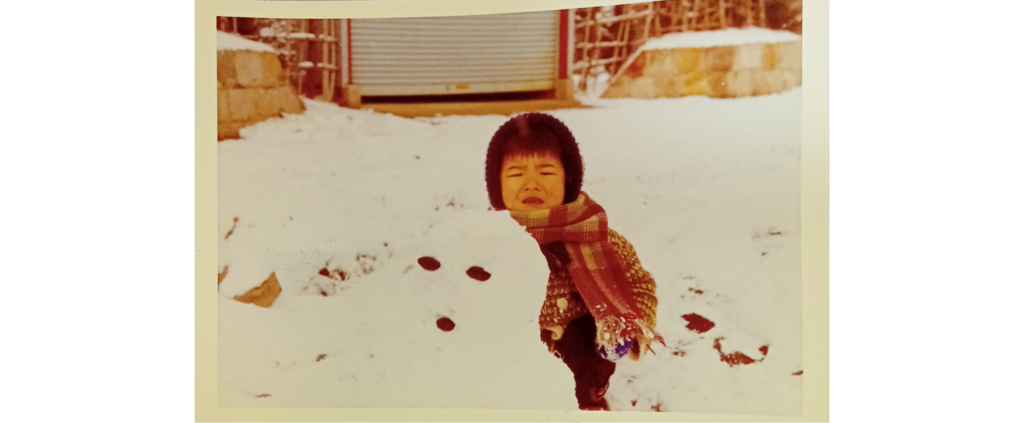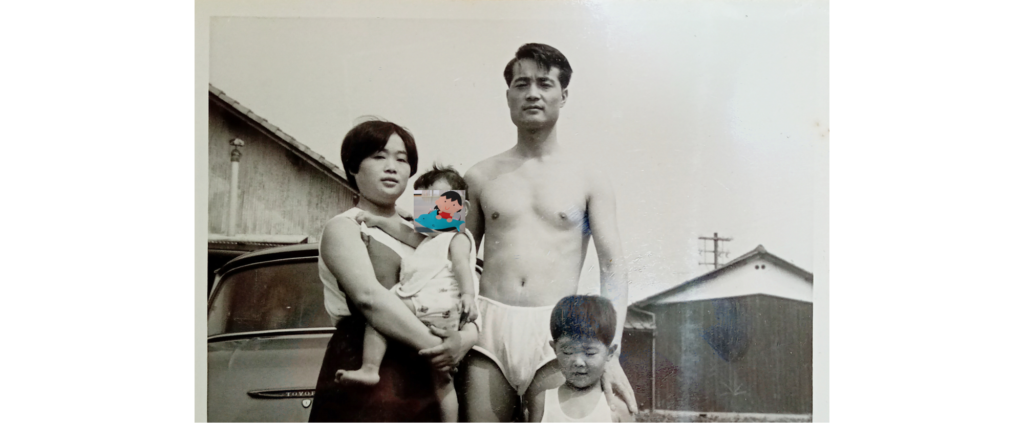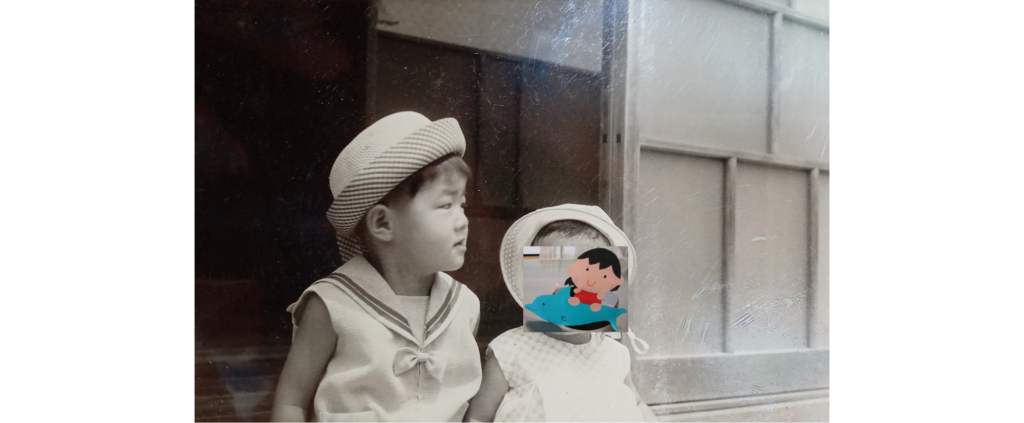
相続税は、相続発生から10カ月以内に、原則現金で一括納付する必要があります
【相続発生から7日以内】
●死亡の届出:死亡届は診断書を添付して市区町村に提出します
【相続発生から3カ月以内】
●葬式費用の整理:香典返しは相続税の計算では葬式費用に含まれません
●遺言書・相続財産・相続人の確認
●相続の放棄または限定承認:この場合は家庭裁判所に申述します。3カ月以内に申述しない場合には単純承認となります
相続放棄:亡くなった人(被相続人)の財産に対する相続権の一切を放棄すること
限定承認:プラス財産の範囲内で負債も相続すること
単純承認:無条件で全財産と全負債を相続すること
【相続発生から4カ月以内】
●亡くなった人(被相続人)の所得税の申告および納付(準確定申告):1月1日から被相続人が死亡した日までの所得を被相続人死亡時の住所地を所轄する税務署に申告・納付します
【相続発生から10カ月以内】
●遺産分割についての相談:遺産分割協議がまとまらなければ家庭裁判所の調停・審判があります。遺産分割協議がまとまらない等で相続開始から10年経過した場合、法定相続分もしくは遺言で定められた相続分により遺産分割されます
●遺産分割協議書作成:どの財産を誰がどのくらい相続するかを決めるために、相続人同士で話し合うことを遺産分割協議といい、この協議がまとまったら、あとで問題が出ないように書面にしておきます。この書面を遺産分割協議書といいます
●遺産の名義変更手続き:2024年4月1日以降、相続した不動産は遺産分割が行われた日から3年以内に登記申請することが義務化されます(2024年3月31日以前に相続した不動産も含みます)
●相続税申告書の作成
●相続税の申告と納付(延納・物納の申請):被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に申告・納付します
【争族と税負担】
相続税の納税額を軽減する効果が大きい配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の評価減の特例を適用するためには、原則として相続税の申告期限(相続開始から10カ月後)までに遺産分割を完了させ、相続税の申告書を提出する必要があります
相続がもめて、遺産の分割が10カ月以内にできませんと
●「配偶者の税額軽減」が適用されません
●相続人によって適用できるかどうかが異なる「小規模宅地等の評価減」が適用されません
そうなりますと、相続税負担が増えて、より多くの納税資金が必要になります
このことから申告期限内のスムーズな遺産分割が大変重要となります
なるべく早い時期に検討をはじめ、遺言書の作成や親族間の話し合いなど、事前に周到な準備を行うことをお勧めします
現在の法令・税制に基づいて作成しており、今後改正等により取り扱いが変わる場合がありますので、ご注意願います。個別の取り扱いにつきましては、所轄の税務署や税理士等の専門家に必ずご確認・ご相談願います